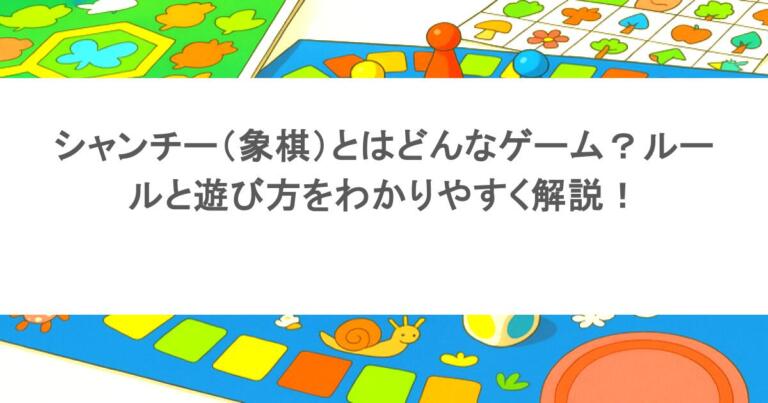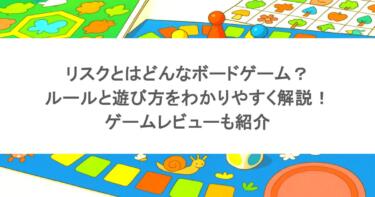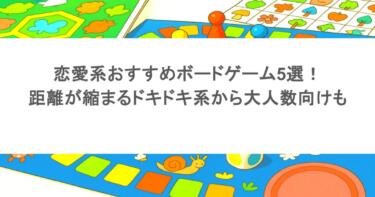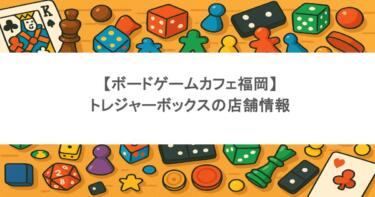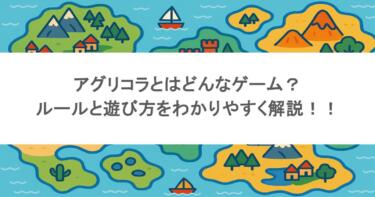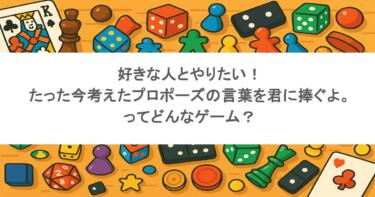「シャンチー」は、古代インドで親しまれていたボードゲームが起源です。約2千年以上前の中国で前身となる遊戯「六博」が生まれ、それから約千年が経過したのちに現在のルールが出来上がりました。日本で広く知られるようになったのは、終戦に伴って日本と中国が国交正常化して以降のこと。例年、全日本シャンチー選手権をはじめ、数々の大会が開催され、注目を集めています。そんな大勢の愛好家がいる「シャンチー」とは、どのようなゲームなのでしょうか。
「シャンチー」の基本情報
「シャンチー」は基本的に2人で対戦するボードゲーム。「中国将棋」という異名がありますが、日本の「本将棋」よりもゲーム展開が早く、短時間で決着がつきやすいです。とはいえゲームの段階ごとに重視しなければならない戦略が異なり、頭をフル回転させる必要があります。日頃から将棋を遊んでいる人でも新鮮な感覚で楽しめるはずです。
プレイ人数:2人
プレイ時間:20分以上
対象年齢: 8歳以上
ジャンル:戦略対戦系
発売年:不明
発祥国:中国
「シャンチー」とはどんなゲーム
「シャンチー」では、プレイヤー2人が紅方と黒方の陣営に分かれ、交互に駒を動かして侵攻します。陣地に見立てたボードの中央付近には敵陣と自陣の境界を示す河川が流れており、駒の種類によっては渡河が不可能です。そのため知略を駆使しつつ、陥落対象である最重要駒を目指さなければなりません。本物の軍師のように駒を動かし、合戦の臨場感を味わえます。
勝利条件
勝利の仕方は以下の3種類。「最重要駒への攻撃を相手が回避できない」「相手が駒をまったく動かせない」「相手が投了を宣言した」、いずれかの条件を満たした時点で勝利となります。尚、最重要駒に対する攻撃(将棋でいうところの王手)を無視する、あえて最重要駒を相手に取られるような動きをとる、これら2つの行為はNGです。
遊び方の流れ
紅方と黒方、各陣営が16個ずつ駒を使うため、合計32個の駒を準備します。各駒を既定の位置に並べたら、ゲーム開始です。紅方のプレイヤーが先手、黒方のプレイヤーが後手となり、手番のたびに好きな駒を1個だけ動かせます。駒は2つの線の交点に表向きにして置かなければならず、裏返しにして使えません。また状況によっては駒の移動先にある相手の駒を取れますが、それをゲーム内で再利用することが不可です。続いては各駒の動かし方を解説します。
「兵」と「卒」
紅方の「兵」と黒方の「卒」は、名称が異なるものの、動かし方が同じです。どちらの駒も自陣では前方のみに進み、1マスぶん移動できます。しかし境界の河川を渡って敵陣に入ると昇格し、行動の選択肢が増加。前方と左右に動けるようになります。とはいえ後退して自陣に戻れないため、安易な侵攻は危険です。敵陣の最奥まで進んだ結果、左右にしか動けなくなり弱体化することを「底兵」や「底卒」と呼びます。
「車」
「車」は「シャンチー」の駒の中で最強といわれており、使い勝手が良好です。将棋の「飛車」と同様に、前後左右に好みのマスぶんだけ動かせます。移動先に自分の駒がある場合には、手前の交点に置くことが可能です。また河川を渡って敵陣に突入した後も、動かし方は変わりません。フットワークが軽いため、万が一の危険があれば早急に退避できます。
「炮」
「炮」は「車」と同じく、前後左右にどこまでも動かせる駒です。「車」と異なるのは、相手の駒を取る方法。シンプルに移動先の駒を取る「車」に対し、「炮」はいずれかの駒1個を飛び越えなければ、相手の駒を取れません。少々イレギュラーな動きをしますが、駒の数が多いゲーム序盤から中盤にかけては重宝します。尚、相手の駒を取らずに、駒を飛び越えて交点に置くことはルール違反です。
「相」と「象」
紅方の「相」と黒方の「象」は、名称が違えど同じ動きをする駒です。斜め前もしくは斜め後ろに進み、2マス先の交点に移動できます。但し移動の途中にいずれかの駒がある場合は、それを飛び越えて侵攻できません。また河川を渡れないため、前進できるのは自陣の境界線まで。敵陣に入れないものの、自陣の防御を固めるうえで、重要な役割を果たします。
「馬」
「馬」は将棋の桂馬やチェスのナイトと似た動きをする駒です。前後左右いずれかに1マス進んだ後、斜め前の交点に移動できます。移動先の候補が多いため、終盤になると価値が上がり、戦略の幅を広げてくれますよ。河川を渡って敵陣でも活躍しますが、1マス進んだところにいずれかの駒がある場合は移動不可能です。「馬」の移動を妨害することは「馬の脚を縛る」と表現します。
「帥」と「将」
紅方の「帥」と黒方の「将」は名称が違えど、動き方が同じ。各陣営の王様を意味しており、最も重要な駒です。しかし、そこまで攻撃力が強いわけではなく、敵陣に入った「兵」や「卒」と同等。上下左右に1マスぶん動けるものの、斜線が引かれている4マスの王城エリアから出られません。
さらに「帥」と「将」が一直線上に並ぶ時には、他の駒を挟む必要があります。この「王様が直に相対してはならない」というルールは他の駒を動かす時にも注意しなければなりません。
「士」
「士」は王様のボディーガードを専門としており、「帥」や「将」と同じく王城エリアから出られない駒です。王城エリアの対角線にそって1マスぶん前進もしくは後退します。水平移動ができません。移動できる交点は5つのみです。用途が非常に少なく地味な駒というイメージを抱かれがちですが、勝敗が決まる終盤では防御と守備を強力にサポートします。
引き分けになるケース
「シャンチー」では、どれだけ相手の駒を取っても再利用できないため、ゲームが進むにつれてボード上の駒が減少します。それゆえ対戦プレイヤー同士の実力が拮抗していると、引き分けになりがちです。ここからは、どのような過程を経て引き分けに至るのか解説します。
双方が引き分けに合意
どちらかのプレイヤーが引き分けを提案し、それを相手が受け入れた時点で成立します。例えば、攻撃に有用な駒が互いにほとんど残っていない場合には、ゲームを続けても勝敗が決まる可能性を期待できないため、引き分けとなるケースが多いです。もちろん勝ち筋が消えていないと思えば、引き分けを拒否してもOK。遠慮せずにゲーム続行の意思を伝えるべきです。
自動限着
万が一どちらかのプレイヤーが引き分けの提案を拒否し続けると、ゲームが停滞し、一向に決着がつきません。このような局面で発動するのが、「自動限着」と呼ばれるルールです。「自動限着」では、既定の手数の間にプレイヤー双方が手を打たず、駒が1個もボード上から減らなかった場合に当該ゲームを引き分けとして扱います。
攻撃の繰り返しに注意
相手の駒を取る際に、2種類の駒で何度も繰り返し追いかけていると引き分けになります。但し1種類の駒を何度も同じ手順で動かし、相手の駒を取ろうとすることは反則負けとなるNG行為です。この反則負けを回避するためには、一手ごとに違う動きを取り入れなければなりません。最重要駒に迫り、勝利が目前となっている局面では、攻撃の繰り返しが起きやすいため注意しましょう。
まとめ
数あるボードゲームの中で最古の歴史を持ち、最多の競技人口をほこる「シャンチー」。プレイするにあたって細かいルールを覚えなければならないデメリットがあるものの、努力を重ねて成長した時の喜びは非常に大きいです。ボードゲームセットだけでなく、オンラインゲームもリリースされているため、すきま時間には「シャンチー」をプレイしてみてはいかがでしょうか。