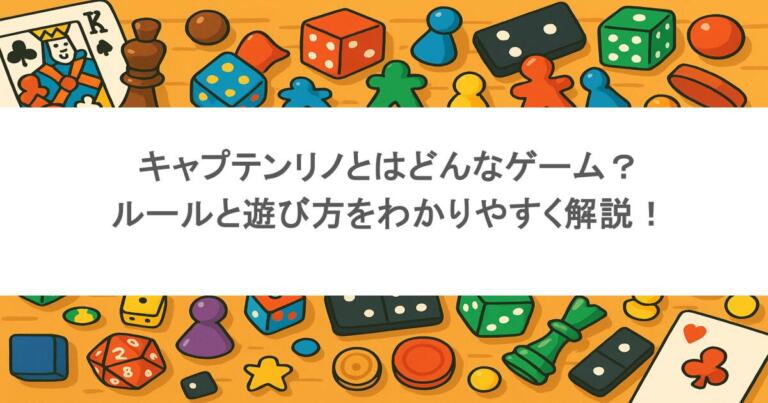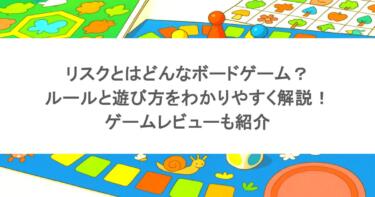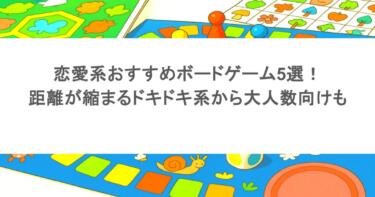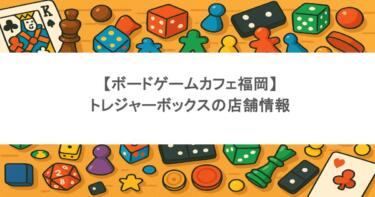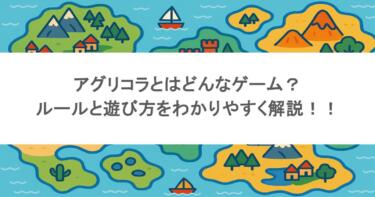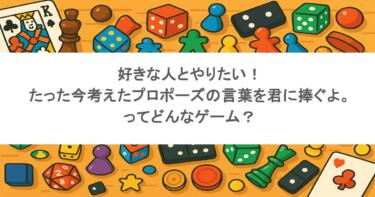ドイツの玩具メーカーであるHABAが2011年に発売したバランスゲーム「キャプテンリノ」。2012年にドイツのボードゲーム年間大賞の準候補に選ばれた話題作です。日本国内では2013年10月に販売が始まり、「5歳児でも楽しめる」「知育におすすめ!」と大好評をはくしています。
いったい「キャプテンリノ」とは、どのようなゲームなのでしょうか。
「キャプテンリノ」の基本情報
「キャプテンリノ」では折り曲げた壁カードと屋根カードを交互に重ね、高層タワーを崩さないように注意しながら建築します。ゲームに慣れてきたら余裕で1メートル以上の高さまで積み重ねられるようになりますが、高層になればなるほどグラグラ揺れてしまい、スリル満点です。また特殊カードの効果によって相手から妨害されるなど、突如として大番狂わせが起きるため、皆でワイワイ盛り上がり楽しい時間を共有できます。
- プレイ人数:2~5人
- プレイ時間:10~15分
- 対象年齢: 5歳以上
- ジャンル:パズル系
- 発売年:2011年
- 発祥国:ドイツ
勝利条件
ゲームの勝利条件は、手札である屋根カード5枚を誰よりも早く置くこと。万が一、ゲームの途中でタワーが崩れた際には、崩れるきっかけを作ったプレイヤー以外の手札を確認し、最も手札の少ないプレイヤーが勝者です。またプレイヤー全員で共有する壁カードの山札を使い切ると、全員が勝者となります。勝利条件が分かりやすいため、就学前児童も直ぐにゲームに慣れて遊べますよ。
遊び方の流れ
出典元:ボードゲームのすごろくや
まずテーブルの中央付近に土台カードを置き、その横に壁カードの山札と、キャプテンリノのコマを用意します。続いて、屋根カードを各プレイヤーに5枚ずつ配布。2人対戦の場合のみ、配布する屋根カードは7枚ずつです。手札である屋根カードは自分だけが表面を見えるようにして持ち、ゲームに臨みましょう。それでは、どのようにゲームが進行するのか解説します。
実行できるアクションは2つ
1番手のプレイヤーは、土台カードの表面に記載されている線に沿って、壁カードを折り曲げて配置します。次に手札である屋根カード中から1枚を選び、壁カードの上に載せます。これで1回あたりのアクションが完了です。2番手以降のプレイヤーは屋根カードに記載されている線に沿って壁カードを配置し、その上に屋根カードを載せます。「壁カードを置いて屋根カードを載せる」というシンプルなアクションの繰り返しでゲームが進行し、難解な操作がいっさいありません。
カードを置く時の注意点
壁カードは、可能な限り土台カードの線に合わせて立体的に配置することがポイント。置く位置がズレたり、わずかにカードが傾いたりすると、タワー全体のバランスを維持しにくくなります。また、屋根カードは土台カードに重なるように優しく載せるのがベストです。真上からタワーを見て、屋根カードの位置を調整しましょう。因みに各カードは両手で置くことを許可されていますが、置く動作の間にタワーの一部となっている他のカードに触れてはいけません。
特殊効果のある屋根カードについて
屋根カードには、壁カードの設置場所のみを示しているスタンダードタイプのほか、なにかしらの効果を発動する特殊カードがあります。例えば、ウロボロスのように矢印が記載されている特殊カードを載せると、順番の方向を転換しなければなりません。しばらく自分の手番が回ってこないだろうと安心していたら、他のプレイヤーが使った矢印の特殊カードによって再び自分の手番になり大ピンチに陥ることも。特殊カードの効果を使いこなし、勝利を目指しましょう。
攻撃力№1のリノカード
特殊カード中で攻撃力が最も高いのは、リノカード。このカードが載せられたら、次の手番のプレイヤーはキャプテンリノのコマを規定の位置に立たせなければなりません。尚コマがすでにタワー内に立っている場合には、そこからコマを取り出して動かす必要があります。ゲーム序盤ならばタワーが低いため、コマを難なく移動させられるのですが、中盤以降は危険がいっぱい。安定しているように見えるタワーでもコマの移動によって各所に傾きが発生しかねません。終盤に形勢逆転を狙うなら、リノカードが有用です。
自分の手番を増やせる2枚重ねカード
特殊カードは周囲を翻弄するタイプが大半ですが、手札としていたプレイヤーのみが恩恵をうけられるものが1種類あります。それは、「2×」というマークが記載されている特殊カードです。このカードを載せたプレイヤーは、続けて手札1枚を消化できます。但し、「×2」の特殊カードを2枚連続して載せられないため、別の特殊カードもしくはスタンダードの屋根カードを手札から選ばなければなりません。
「キャプテンリノ」巨大版も面白い?
「キャプテンリノ」巨大版は通常版のサイズを約3倍にしており、カード1枚1枚の重量感が半端ないです。カードを積み上げていく中でモノづくりの楽しさも体感できます。さらに、瞬く間にタワーの高さが身長を超え、最高3メートルほどに達するため、椅子の上に立ってプレイしなければなりません。見た目の迫力やプレイ感が抜群です。通常版よりもやや価格が高額になるぶん、とことんゲームの醍醐味を味わえます。
「キャプテンリノ」のレビュー
カードゲーム「UNO」とバランスゲーム「ジェンガ」の要素が見事に融合している「キャプテンリノ」。いかにしてタワーを高く積み上げるべきか周囲と協力しながら、いち早く自分の手札を消化するために考えなければならないため、子供の脳を活性化させる効果も望めます。ここからはプレイするメリットや不満点など、レビューを確認していきましょう。
老若男女がルールを把握しやすい
ゲームの基本は、カードを積むこと。特殊カードの使い方や効果に関しても、1~2回ほどプレイすれば把握できます。ルール全般に複雑な部分がないため、就学前児童からシニア層まで幅広い年代がプレイしやすいです。またゲームで使うカードが紙製なので、タワーが崩れても安全。大きな音が発生する、プレイヤーがケガをするといったリスクは、ほとんどありません。それゆえ家族みんなで遊ぶ時には「キャプテンリノ」が定番という人も多いようです。
コマの移動にドキドキ
リノカードおよびキャプテンリノのコマは、タワーのバランスを崩す要因の1つ。とくに、コマが壁カードにギリギリ接するような位置に立っており、そこからコマを引っ張り出して移動させることは、至難の業です。指が壁カードに触れるとルール違反になるため、細心の注意を払わなければなりません。リノカードがゲームを盛り上げるものの、同じプレイヤーにばかり渡ってしまうと不公平感が生じ、微妙な空気になるというデメリットがあります。
カードを折るクセ癖がついてしまう
「キャプテンリノ」では壁カードを半分に折る行為がゲームの一部です。そのため幼い子供たちが「キャプテンリノ」を何度もプレイすると、カード=折って遊ぶものと勘違いする可能性があります。トランプや名刺など、「キャプテンリノ」に関係ない他のカードまで子供が折ってしまわないように、しっかり説明することが重要です。
まとめ
ドイツ発祥のバランスゲームである「キャプテンリノ」。2013年に日本版が発売されて以降は、日本国内でも多くの人に親しまれています。ルールがシンプルだからこそ奥深い魅力を持っているため、リピーターが続出中です。とくに、すべての壁カードを積み上げて、タワーを完成させた時の感覚は格別です。ぜひ最高記録の更新を目指しながらプレイしてください。