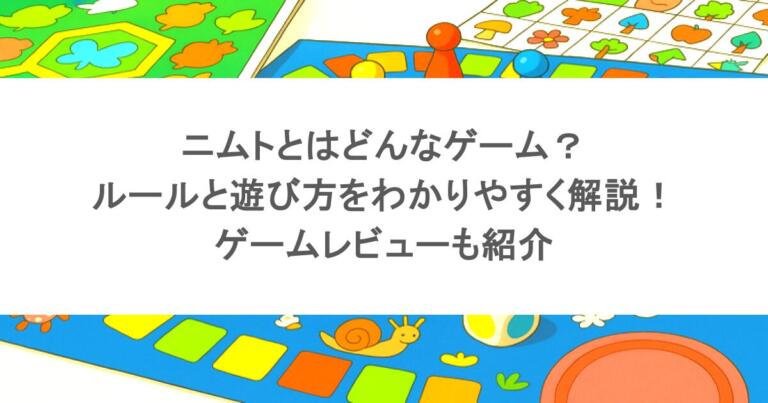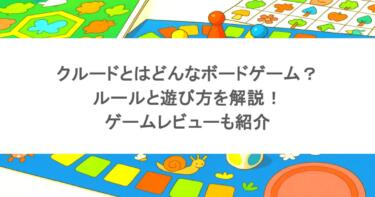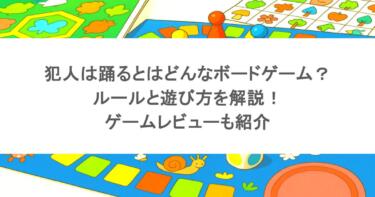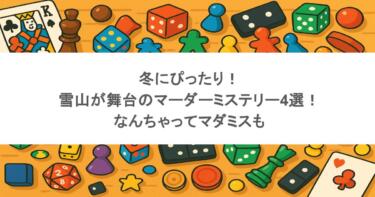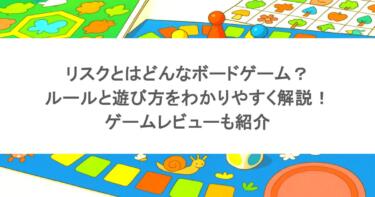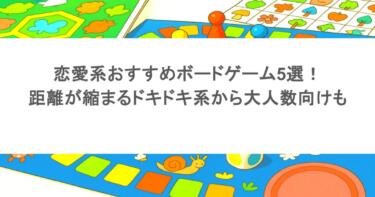ドイツ語で「6枚とりなさい!」を意味するカードゲーム「二ムト」。ドイツ出身のゲームデザイナーであるヴォルフガング・クラマーさんらが手がけ、Amigo社が1994年に発売しました。同年にドイツゲーム大賞で第1位を獲得するなど、世界規模で高い評価を得ています。そこで今回は、「二ムト」のルールやゲームレビューなどをまとめました。
「二ムト」の基本情報
「二ムト」はボードゲーム専門店・メビウスゲームズが取り扱いを開始して以降、日本人のファンが急増。競技性に特化したルールのもとプロリーグ公式戦が開催され、熟練者による熾烈な戦いが繰り広げられています。大人になると真剣勝負を味わえる機会は滅多にありません。だからこそ、どこにでも持ち運べるサイズで、気軽にドキドキ感を体験できる「二ムト」に多くの人が夢中になっているようです。
プレイ人数:2~10人
プレイ時間:30分
対象年齢: 8歳以上
ジャンル:バースト系/戦略対戦系
発売年:1994年
発祥国:ドイツ
「二ムト」とはどんなゲーム?
「二ムト」は幅広いプレイ人数と共に、分かりやすいルールが特徴です。プレイヤー全員が手札の中から1枚を選び、小さい数字のカードから順に場に並べます。場に並べられるカードの列と枚数、そして配置方法には「二ムト」独自のルールがあり、それを守らなければペナルティ発生。当該プレイヤーが減点対象となるカードを引き取られなければなりません。白熱の読み合いが発生しますが、ゲーム上級者が簡単に勝利できるわけではなく、ひらめきや運も対戦の肝となります。
ゲームの勝利条件
ゲーム開始時点、各プレイヤーは66ポイントを所有しています。このポイントはペナルティとして引き取ったカードに描かれている牛の頭数ぶん減らされ、ゲーム中いっさい補充がありません。ゆえにプレイヤーの内だれか1人がポイントを失った時点でゲーム終了となります。この時に、残っている所有ポイントが最多のプレイヤーの勝利です。ラウンド終了のたびにマイナス点を計算する必要があるため、あらかじめ点数表を作っておくと便利ですよ。
遊び方の流れ
まずは、1から104までの数字が記載されているカード104枚を裏向きのまま束ねて十分にシャッフルし、各プレイヤーに10枚ずつ配布。続いてランダムに選んだカード4枚を表向きにして1枚ずつ縦方向に並べたら、いよいよゲーム開始です。プレイヤーそれぞれが自分の手札を確認し、いずれか1枚を選んで一斉に場に出します。カードを場に配置する時には、いくつか細かいルールがあるため注意しなければなりません。
カードを場に配置する時のルール
プレイヤー個々が出したカードは、数字が小さいものから順番に処理し、各列の最後尾に配置します。但し、出したカードよりも小さく、近似値の右隣でなければ配置できません。この独自性に富んだルールにより、ゲーム展開が非常に読みにくいです。
出典元:ボードゲームルール超簡単説明
上記のYouTube動画(1分05秒あたり)で詳しく説明されているため、参考にしてください。
6枚目を置くとペナルティ発生
各列に配置できるカードの枚数は5枚が限度です。そのため、出したカードが列の6枚目となった場合には、ペナルティが発生します。既に配置されているカード5枚を当該プレイヤーが引き取らなければなりません。引き取ったカードは減点対象のため自分の近くに置き、手札に混ぜることがNG。また、出したカードは新たな列の1枚目として配置し、4列を維持する必要があります。
カードを置けない場合には
ゲームが進行すると、どこにもカードを置けないことがあります。その事例とは、最後尾のカード全ての数字が出したカードよりも大きいケース。このケースに遭遇した際には。いずれか1列を当該プレイヤーが引き取り、そこに出したカードを置かなければなりません。引き取ったカードは、もちろん減点対象です。そのため出来る限りマイナス点が低い列を選びましょう。
ゲーム終了のタイミング
カードを選んで並べるという一連の行動を手札が無くなるまで繰り返し、1ラウンド終了です。各プレイヤーが引き取ったカードのマイナス点を合算し、現時点のポイントを計算します。その後、全てのカードを回収して、2ラウンド目を開始。ラウンド終了のたびにマイナス点を計算し、いずれかのプレイヤーがマイナス66点以下になっていれば、そこでゲーム終了です。
マイナス点の計算方法
マイナス点を計算する時、カード中央に大きく記載されている数字は、関係ありません。着目するべきは、カードの端に記載されている牛マーク。この牛マークの数がマイナス点となります。背景の色によってマイナス点が異なり、白色が最も低いマイナス1点。その他のカラフルな色はマイナス2~7点です。牛マークに十分に注意し、いかにして失点を少なく抑えるかが、勝敗のカギとなります。
ゲームレビューを紹介
予想外の展開にプレイヤーみんなで盛り上がるのが「二ムト」の醍醐味の1つです。「この数字を出せば絶対に安全だろう」と推測していても、たいてい思い通りにはいきません。とくに参加プレイヤーが8人以上の場合には、先読みが非常に難しいです。そのため、他のプレイヤーが出したカードによって思いがけない大きなマイナス点を背負わされることも…。非日常的なドキドキワクワク感を味わえます。
5人以下のプレイでは戦略が重要
8人以上でプレイすると運の要素が強くなる一方で、5人以下の場合には戦略や駆け引きが重要です。極端に大きい数字の手札をいずれのフェーズで処理するべきか、相手のカードの並べ方を踏まえると次は手札を消化しようかなど、色々と考えさせられます。場の状況と手札を見比べたすえ、自分の思惑が見事に的中した際には、痛快です。
子供も楽しめる
「二ムト」のルールは数字の順番を理解できれば、直ぐに覚えられるシンプルな内容です。小学校低学年の子供や、ボードゲーム未経験者でも短時間で慣れて、ゲームの面白さをしっかり体感できます。また、ラウンド回数を調整してプレイすれば、短時間でサクッと楽しむことが可能です。幼い子供は長丁場になると集中力を切らして飽きてしまうため、3ラウンド程度がオススメですよ。
ヴァリエーションルールも面白い
実は「二ムト」には基本のルールと共に、やりごたえ抜群のヴァリエーションルールが複数あります。例えば「戦略」ルールは、プレイヤーの人数に合わせて使うカードの数字と枚数を制限。4人プレイならば数字が1~44のカードしか使いません。そのためシビアな読み合いが必須となり、ゲーム展開もスリリングです。因みに、いずれのヴァリエーションルールもプレイヤーの好みに合わせて自由にアレンジOK。無限に遊びの幅を広げられるため「二ムト」の人気が衰えないのでしょう。
まとめ
「二ムト」は分かりやすいルールと遊び方が大きな魅力です。老若男女を問わず、誰もが楽しくプレイできます。参加メンバーや人数によっては頭脳戦が繰り広げられるものの、ゲームの終盤に大逆転が起きることもあり、予期せぬ展開にドキドキワクワクの連続です。カードゲームに興味がある人は、「二ムト」のプレイを検討してみてください。